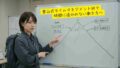「どうすれば、職場で信頼される人になれるのか?」
そんな問いを抱える社会人1年目のあなたに届けたい話があります。
上司や先輩との会話で緊張してしまったり、うまく返事ができなかったり、報告のタイミングがつかめなかったり。
「コミュニケーション力が大切」とは言われても、その“本質”がつかめずに戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
実は、登山の世界には、ビジネスに通じる“聴く力”と“伝える力”が詰まっています。
自然の中では、言葉以上に大切な「意思疎通」のスキルが問われます。
その力を知ることで、あなたの職場での立ち居振る舞いは、確実に変わります。
今回は、登山をヒントに、社会人1年目が身につけたいコミュニケーション力の本質に迫ります。
H2:社会人1年目に求められるコミュニケーション力とは?

「ただ話すだけでしょ?」
そう思っていたコミュニケーションが、実は仕事の成果を左右する最重要スキルだった――。
そんな衝撃を受けたことがある人もいるかもしれません。
社会人にとっての“伝える・聴く”は、単なる会話術ではありません。
それは「信頼を育てる技術」であり、「自分の意思を届ける力」であり、「相手の心を受け取る感性」でもあります。
特に1年目は、受け身でいると「わかっていない」と誤解されがち。
話し方だけでなく、聞き方、反応の仕方までが、あなたの印象を形作ります。
ここでは、なぜコミュニケーション力が新人にとって決定的な差になるのかを、具体例とともに見ていきましょう。
指示待ちでは信頼されない理由
自分から動ける人と、待っているだけの人。
その差は、単に「行動力」の違いでは語れません。
本質的には「聴く姿勢」の違いが、その人の信頼度に大きく影響を与えます。
上司や先輩の言葉に対して、ただ受け取るのではなく、「なぜそうなのか」「次にどうつなげるか」と考えながら聴くこと。
これが、“指示を待つだけの人”と“信頼されて動ける人”との決定的な違いを生みます。
もし指示が抽象的であれば、自分から「このやり方で合ってますか?」と確認する。
終わったあとも、「他にお手伝いできることはありますか?」と一言添える。
こうした積極的なやりとりが、相手に安心感を与え、「この人に任せられる」という信頼へとつながっていきます。
また、たとえ業務にまだ慣れていない段階でも、「どうすれば力になれるか」を常に考える姿勢は、確実に評価されます。
自分から動くことは、単なる“行動”ではなく、“相手への関心”の現れなのです。
聞き上手・伝え上手は評価の分かれ目
ただメモを取るだけでは、“聞いている”とは言えません。
本当に聞いているというのは、相手の話の本質を理解し、その意図を正確に汲み取る姿勢を持っていることです。
要点を押さえて聞き、必要があれば質問することで、相手に「きちんと理解しようとしている」と伝わります。
質問もただ聞くのではなく、「今の説明で、●●という点はこういう解釈で合っていますか?」と、自分の解釈を交えた質問をすることで、より深い対話が可能になります。
また、聞いた内容をそのまま返すのではなく、相手が理解しやすい言葉に変換して伝えるスキルも必要です。
たとえば、専門用語を使わずに説明したり、図やたとえ話を交えるなどの工夫も大きなポイント。
この“要点を押さえた聞き方”と“伝わる話し方”のセットができて、はじめて「この人、わかってるな」と思われるのです。
つまり、「聞く」と「話す」の間には、常に“考える”が挟まっているということ。
このプロセスを意識できるかどうかが、評価の分かれ目になります。
雑談も立派なスキル
昼休みやすれ違いざまのひと言が、チームの空気を変えることがあります。
それは特別な話題でなくても構いません。
「今日は寒いですね」でも、「ランチ何にしました?」でもいいのです。
大切なのは、その言葉が相手に「あなたの存在を気にかけていますよ」と伝える“サイン”になること。
人は誰しも、職場で孤立しているような感覚を持つと、不安になりやすいものです。
そんなとき、ふとした雑談やさりげない声かけが、その心をふっと軽くしてくれることがあります。
たとえば、顔を合わせた瞬間に「お疲れさまです」と笑顔で言われるだけで、気持ちが和らぎ、安心感が生まれます。
こうした日常のちょっとしたコミュニケーションが、チーム内の信頼関係をじわじわと築いていくのです。
何気ない雑談や挨拶の積み重ねが、職場全体に“話しかけやすい空気”を生み出し、円滑な連携の土壌を育ててくれます。
H2:登山におけるコミュニケーションの重要性

標高が上がるほど空気は薄くなり、体力も削られていく。
足が重くなり、思考も鈍くなりがちな状況では、判断ミスが命取りになることも少なくありません。
そんな過酷な状況下で、人は「言葉の力」に支えられています。
一言の声かけ、一瞬の合図が、チーム全体を救うことさえあるのです。
登山では、些細なひと言がチームの命を守ることもあるというのは、決して大げさな表現ではありません。
「大丈夫?」「あと少しで休憩だよ」など、励ましや共有の言葉が、メンバーの精神的な支えになります。
それだけではなく、「水が残り少ない」「足元に注意して」といった情報の伝達が、事故を防ぐ要にもなるのです。
ビジネスの現場と違い、登山には命がかかっている。
その緊張感の中で交わされる言葉は、軽さを許さず、本質を突く必要があります。
だからこそ、伝える力・聴く力の“本質”がありありと浮かび上がってくるのです。
ここでは、そんな山の現場から見えてくる、リアルで実践的なコミュニケーションの在り方を、改めて紐解いていきましょう。
協力しなければ遭難する!登山の連携力
「ちょっと疲れた」「水が少なくなってきた」
こうした小さな発言の積み重ねが、安全な登山を支えています。
一見、些細なつぶやきに見えるかもしれませんが、登山の現場では重要な“情報共有”の一部です。
こうした声をきっかけに、休憩のタイミングを調整したり、ルート変更を検討したりと、状況判断に結びつくことも多くあります。
特に疲労や脱水は、遭難や事故の大きな原因となるため、初期の小さなサインを見逃さないことが重要です。
そのためには、日ごろから「声を出すこと」がチーム内で推奨され、受け入れられている必要があります。
また、声をかけられた側もそれを軽んじず、「ありがとう」「少し休もうか」と肯定的に反応することで、互いの信頼が深まります。
互いに声をかけあう文化があることで、チーム全体が“無理な行動”や“孤立”を避ける空気を自然とつくり出しているのです。
まさに、「小さな声が、大きな安全を生む」典型的な例と言えるでしょう。
リーダーとフォロワーの役割分担
登山では、全員が自由に動くと事故の原因になります。
自然の地形や天候、体力の差など、さまざまな要素が入り混じる登山では、個々の判断だけで行動するとチームの統率が乱れ、転倒や遭難といった重大なリスクにつながりかねません。
だからこそ、チーム全体で“どう進むか”を常に共有し合う姿勢が欠かせません。
先頭と最後尾、中間にいる人、それぞれの役割を理解し、それぞれが責任を持って行動することが求められます。
たとえば、先頭はペースを決める役割を担い、最後尾は遅れている人がいないか確認し、中間は情報の伝達をスムーズにするハブの役割を果たします。
それらの役割が機能するためには、常に声をかけ合い、情報を補い合いながら進む必要があります。
ビジネスにおいてもまったく同じことが言えます。
プロジェクトや業務の中で「自分のポジションが何なのか」を理解し、その期待に応える動きができるかどうかで、チームの完成度は大きく変わります。
また、その役割を共有することで、他メンバーが補い合える仕組みが生まれ、結果として大きな信頼と成果につながっていきます。
非言語コミュニケーション(アイコンタクトや声かけ)
風が強い、距離がある、声が届かない。
そんな時でも、アイコンタクトや手の合図で意思を伝える場面が多くあります。
「行けそう?」「ストップして」といった簡単なメッセージでも、目を合わせたり、手を振るだけで驚くほど正確に伝わるものです。
とくに危険な箇所を通過する時や、後続がついてきているかの確認など、非言語のやりとりが命綱になることもあります。
これは職場でも同じです。
うなずき、目線、姿勢、表情──どれもが言葉を補う大切なコミュニケーション手段です。
たとえば、会議中に相手の話にしっかりうなずいたり、目を見て聞いているだけで、相手は「ちゃんと伝わっている」と感じ、安心します。
逆に、無表情や無反応でいると、「関心がないのかな?」「理解していないのかも」と不安にさせてしまいます。
非言語のサインは、相手に「ちゃんと聞いていますよ」と伝えてくれるだけでなく、あなたの信頼性や真剣度をも伝えているのです。
職場という“言葉が飛び交う空間”において、実は“言葉を使わないやりとり”こそが、円滑な人間関係を築くカギになる──そんな登山での学びを、ぜひ日常にも生かしてみてください。
H2:登山から学ぶ“伝える・聴く”スキルの実践方法

登山で得られる学びを、日常や職場でどう活かせばいいのか。
そのヒントは、登山で当たり前のように行われている「小さな確認作業」に隠されています。
たとえば、休憩のタイミングや進行ルート、水分補給の有無など、仲間と確認しながら進む行為。
これらは一見些細に見えても、結果的に事故を防ぎ、全体のパフォーマンスを底上げする大きな要素になります。
職場でも同じように、「今、どのタスクに取り組んでいるのか」「いつまでに終わりそうか」「不安な点はあるか」といった日常的な声かけや共有が、スムーズな連携につながります。
また、登山中の確認は“相手の体調やペースを気にかける”という思いやりの表現でもあり、チームワークの本質的な部分を支えています。
このような小さな声かけや報告を習慣化することで、誤解やすれ違いといった“人間関係のひび”を未然に防ぐことができます。
そして、結果として全体のパフォーマンスが高まり、信頼感にあふれたチームが形成されていくのです。
では、そんな登山式の確認習慣を、職場でどのように取り入れていけばよいのか。
具体的な行動例を次からご紹介します。
状況報告・確認を習慣化する
「10分後に休憩しませんか?」
「このルートで合ってますか?」
登山ではこうした報告と確認が頻繁に行われます。
このようなやりとりは単なる情報の伝達ではなく、メンバー間の信頼を築き、安心感を生み出す行動でもあります。
たとえば、休憩のタイミングを提案することで、相手の体調を気遣っていることが伝わりますし、ルート確認の声かけは自分の判断だけに頼らず、仲間と一緒に進んでいるという協調性の表れでもあります。
これをビジネスに置き換えると、「この方向性で進めて大丈夫ですか?」「●日の会議に間に合うように進捗はこうです」などの“共有”や“確認”が該当します。
一見地味に思えるこうしたやりとりも、周囲からの信頼を得るためには非常に重要なアクションです。
また、何か変更があった際には「このあと、仕様が変わるかもしれません」といった未来の可能性を含めた共有も有効です。
こうした“予告と報告の習慣”があるだけで、チームの混乱は大きく防げます。
日常的に小まめな確認を重ねる姿勢は、円滑なコミュニケーションの基盤を築くと同時に、リスク管理能力の高さとしても評価されるのです。
相手の立場で考える質問力
「Aさん、この資料、何を重視して見ていますか?」
こうした質問は、相手の期待に沿った行動を導きます。
ただ仕事をこなすのではなく、「何が期待されているのか」「どこに焦点を当てるべきか」を明確にすることが、成果を最大化するうえで不可欠です。
聞くことで、相手の価値観や判断基準が見えてきます。
たとえば、スピード重視なのか、品質優先なのか。
あるいは数字に強い関心があるのか、ストーリー性を重んじているのか。
そうした細かな“重視ポイント”を知ることで、無駄な修正やすれ違いが減り、作業効率も格段に上がります。
また、このような質問を通じて「相手の意図を尊重している」という印象を与えることができるため、信頼関係の構築にもつながります。
質問力とは、単に疑問をぶつける力ではなく、「相手の目線で考える力」のあらわれでもあるのです。
その積み重ねが、あなた自身の動きにも明確さと納得感をもたらしてくれるでしょう。
★円滑な報連相のコツとツール(Slack・LINE WORKS等)
口頭だけでは情報が漏れることもあります。
とくに複数人が関わるプロジェクトや、タイムラグのあるやりとりでは、聞いた・聞いてないの認識ズレが起きやすく、トラブルの原因になりかねません。
そのため、口頭に頼りすぎず、チャットツールを併用してタイムスタンプ付きでやりとりを残すのが、よりスマートで安全な方法です。
文字として残すことで、自分自身の確認にも使えますし、後から見返したときにも「言った・言わない」の水掛け論を回避できます。
また、特にSlackやLINE WORKSといったビジネス向けチャットツールは、既読機能やメンション通知、チャンネル別の情報管理などが充実しているため、報連相の精度とスピードを同時に高めることができます。
資料やリンクもまとめて共有しやすく、会話履歴が残るため、タスクの見落としや勘違いも防げます。
さらに、口頭で伝えるのが難しいニュアンスや感謝の気持ちも、スタンプや絵文字を活用することで、やわらかく表現できるという利点もあります。
これらのツールを上手に活用することで、単なる連絡手段ではなく、信頼と円滑なチーム運営を支える“土台”として、報連相を機能させることが可能になります。
H2:新人が避けたいコミュニケーションのNG例

どんなに明るく挨拶していても、根本のやりとりにズレがあると、信頼関係は築けません。
表面的な礼儀や言葉遣いが丁寧でも、コミュニケーションの“芯”に食い違いがあると、相手は違和感を抱きます。
「ちゃんと話しているのに、なぜかうまくいかない」
そう感じる場面があるなら、それは伝え方や聞き方の“質”が影響しているのかもしれません。
特に新人のうちは、まだ信頼の土台ができていない分、ひとつひとつのやりとりが相手の印象に直結します。
だからこそ、「やってはいけない伝え方・聞き方」を避ける意識が不可欠です。
これらの失敗は、登山においても同様にリスクを招きます。
声をかけるべきタイミングで黙っていたり、状況を誤解したまま進んでしまったり。
小さなミスが大きな事故につながるように、職場でも些細な伝達ミスが信頼の損失やプロジェクトの遅延を招くことがあります。
ここでは、登山や職場で実際に見られる「やってしまいがちなNG例」を紹介し、どこに落とし穴があるのかを探っていきます。
質問できない・していないふり
「今さら聞けない」「聞いたら怒られそう」
そんな思いから、わからないまま放置してしまうことがあります。
しかし、理解できないまま業務を進めることは、結果的に自分自身を苦しめることになります。
細かい内容の誤解や、作業の進め方のズレが積み重なれば、やがて大きなトラブルや信頼の損失へとつながる恐れがあります。
しかも一度ついた誤解やミスの印象を取り戻すには、時間も努力も必要になります。
だからこそ、「すみません、もう一度教えてください」というひと言は、自分を守るための“最強の武器”なのです。
たとえ聞きづらくても、最初にきちんと確認しておくことが、後の安心と自信につながります。
この一歩を踏み出せる人は、自ら学び続ける力を持っている人です。
恥ずかしさや恐れを超えて質問するその姿勢こそが、確かな成長の証なのです。
無言・リアクション不足
返事をしない、うなずかない、表情が乏しい。
こうした態度は、相手に「届いてないのかな?」「ちゃんと聞いてくれているのかな?」という不安を与えてしまいます。
特にオンライン会議などでは、相手の顔や声の反応に頼る場面が多いため、リアクションの有無がコミュニケーションの成否を分けることさえあります。
うなずく、相づちを打つ、「なるほど」「わかりました」と一言添える──これらはすべて、相手に安心感を与える重要な要素です。
言葉がなくても、笑顔や表情、姿勢の変化ひとつでも、「聞いてるよ」「わかってるよ」と示すことができます。
こうした“受け止める姿勢”を見せることで、相手の話す意欲や信頼度は大きく変わってきます。
反応のない相手には、誰しも話しづらくなるもの。
だからこそ、小さなリアクションの積み重ねが、良質な関係性と信頼の土台をつくるのです。
指示の確認を怠る
「○○をしておいて」と言われて、そのまま受け取って失敗した。
こうしたケースは、特に新人にとって非常に起こりやすいミスのひとつです。
なぜなら、経験や背景知識が十分でない段階では、同じ言葉でも人によって捉え方が異なることがよくあるからです。
たとえば「まとめておいて」と言われた時に、資料を印刷するのか、内容を要約するのか、フォルダに整理するのか──人によってイメージする“まとめ方”は違うことがあります。
こうしたあいまいさをそのままにして作業を進めてしまうと、「思っていたのと違う」と指摘され、やり直しになるだけでなく、「報告や確認をしない人」という印象を与えかねません。
だからこそ、「○○という解釈で合ってますか?」と一度確認を入れるだけで、誤解の芽を事前に摘み取ることができ、信頼関係の構築にもつながります。
ほんの5秒の確認が、のちの数時間のやり直しを防ぎ、あなたの評価を高めることにもなるのです。
H2:まとめ|登山式コミュニケーションで信頼される社会人に

登山も仕事も、目的地に向かう「チームの旅」です。
その旅を円滑に進めるために欠かせないのが、コミュニケーションという“見えない橋”です。
うまく話すことよりも、「うまく通じる」ことのほうが、ずっと難しくて大切です。
言いたいことをただ並べるだけではなく、相手の立場や理解度を想像しながら伝える努力こそが、伝わる力を育てます。
また、「伝える」よりも「伝わる」こと。
それを意識することで、あなたの言葉がぐっと実感を持って届くようになります。
ほんの少しの声かけが、チームに安心をもたらし、信頼を築きます。
たとえば「お先にどうぞ」「困ってたら教えてね」そんな一言が、人の心を動かします。
うなずきやアイコンタクト、返事のタイミングや、視線の向け方──。
どれもが、信頼という名の“地図”をチーム全体に描いていくための大切な手段です。
そして報告・連絡・相談のタイミングを逃さないことは、登山の安全を守るのと同じように、職場に安心感と連携力を生み出します。
登山のように、互いのペースを尊重しながら、一歩ずつ確実に歩を進めていく。
そんな“伴走する意識”を持つことが、社会人としての信頼構築の核心なのです。
社会人1年目のあなたも、気づけば職場でチームを見守り、導ける“登山リーダー”のような存在になっているかもしれません。
📎この記事は「登山から学べる!社会人1年目の7つのスキル」シリーズの第2弾です。
▶ 第1弾「【社会人1年目必見】登山式タイムマネジメント術で時間に追われない働き方へ」もぜひご覧ください!